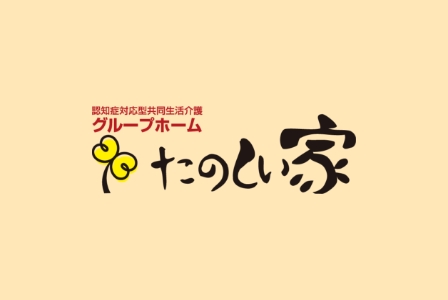学童とは何が違うの? 発達支援サービス 「放課後等デイサービス」について解説

「放課後等デイサービス・児童発達支援」の施設では、障がいをもつ未就学児や小学生~高校生などが、日中や放課後の時間を過ごしています。自治体によって施設状況などに違いがあるので、今回は兵庫県西宮市を例に挙げながら、この施設について紹介します。
また、弊社施設での実例や、西宮北口で2025年8月に開設する放課後等デイサービス・児童発達支援「リールスメイト」、2025年秋開設の個別療育等支援サービス「リールスプラス」のご案内も最後に掲載しますので、よろしければご覧ください。
障がいをもつ子どもに対しての、国の考え方
乳幼児期に比較的判明しやすい知的・身体的障がいも含め、さまざまな障がいに関する調査が最近、国によって定期的に行われています。
これは、親や家族だけへ子育てを任せきりにするのでなく、行政を中心に地域全体で「障がいをもつ子もそうでない子も差別することなく一緒に」見守り、育てていくことが推進されているからです。
少し硬い文章になりますが、そういった国の理念を最初にまずご紹介しておきます。国のレベルでこれを推進しているので、もし、悩みを抱える保護者の方がおられるなら、抱え込まずに周囲へ助けを求めていただきたいと思います。
〇障害児支援※1
障害児の健やかな育成を支援するため、障害児及びその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制を構築することが重要です。(中略)
また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する観点等を踏まえ、文部科学省や厚生労働省と連携し、一人ひとりの教育的ニーズを踏まえた特別支援教育との連携の促進や、一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行を図るなど、切れ目ない支援の充実を図るとともに、医療的ケアが必要なこどもや様々な発達に課題のあるこども等について、医療、福祉、教育が連携して対応する環境整備に取り組んでいきます。
注:
※1) こども家庭庁「障がい児支援」概要
https//www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien
「安心して過ごせる居場所が欲しい」保護者の声
主に小学校1~3年生の子どもたちが放課後を過ごすための公的な「学童」施設(正式名称「放課後児童クラブ」)は、地域の学校内での併設(別の建物か、空き教室を使用するなど)が一般的なようです。そのため移動時の安全確保への不安は少なく、場所慣れについてもあまり問題はなさそうです。
一方、学童では違う学年の子どもたちが混ざって過ごす、仲の良いお友達が一緒に通うとは限らない、人数が多く落ち着かない、といった理由から、通うのを嫌がる子どもたちも一定数、いるようです。
学童が放課後時間の選択肢から外れる場合、次の選択肢として、民間の学童や習い事、あるいはキッズシッターなどが考えられます。
さらにもし、医師から障害をもつと認められるようであれば、障がいの手帳(障害をもつことを自治体が確認し発行するもの)を持っていなくても、「放課後等デイサービス」へ通うことが選択肢の一つとなります。
西宮市で利用できる障がい児向け放課後支援サービスとは?
今回、例に挙げる兵庫県西宮市では、子育て全般と、障がいをもつ子どもに対する親の相談窓口や子どもの生活・教育に関する支援が行われています。
障害のあるこどものために
https//www.nishi.or.jp/kosodate/kosodate/shogainoarukodomo/index.html
西宮市ではいちばん最初、とっかかりの相談窓口として「こども未来園」という施設が設けられています。ここでまず保護者の相談にのり、それぞれの子どもに、必要があれば個別支援等へつなげる体制のようです。参考までに、その仕組みを紹介する西宮市のサイトページを挙げておきます。
西宮市立こども未来センターでの相談
https//www.nishi.or.jp/kenko/fukushi/sodammadoguchi/shogaisodanmadoguchi.html
民間学童とどう違う? 障がい児のための支援内容
国が定めた障がい児に対する福祉サービス※2は、
知的障害児/難聴・ろうあ児/盲児/肢体不自由児/重症心身障害児/自閉症児
などに対して実施されています。こうした「身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)」と、その家族に対する支援の種類は
・通所支援<市町村・政令指定都市・中核市※3管轄>
・入所支援<都道府県管轄/福祉型・医療型>
・訪問支援<通所が困難な児童・生徒向けの支援>
・相談支援<サービスを受けるための計画
(プログラム)を立てたり、利用中、各種の相談にのる>
に分類されます。これらのサービスは、子ども一人ひとりの状態・状況に沿う個別の支援計画を立ててから、その子の成長・発達に合うプログラムなどが提供されるルールとなっています。
そして上記の「通所支援」の一つ、主に就学後~18歳の障がい児を対象とするのが「放課後等デイサービス」です(なお、就学前の子どもの通所支援では「児童発達支援」という枠組みもあります)。
一方、一般的な「学童」施設で、公的に設立されたところでは「そこに通う子どもたち全般」に対するルールを守ることが基本となっています。障がいをもつ子どもは「特別な配慮を必要とする児童」として、可能な施設のみが受け入れ、見守りの担当者をつけたりもするようです。
公的な学童施設は子どもたちの「安全な居場所」という設定なので、基本的には学びのプログラムなどがなく、子どもたちは一定のお約束やルールに沿って、自由に過ごします(自治体によって異なります)。
障がいをもつ子たちも、子ども同士の自然な関わり合いの中で学びを得ていけるよう見守られます。見守りのみかどうかという点が、公的な学童施設と放課後等デイサービスの最も大きな違いと言えます。
さらに民間の学童施設になると、一般的なプログラムとして学習能力の向上や心身発達を目指すものなどが用意されるようです。そして障がい児の受け入れは「あり」と「なし」があります。「あり」のところでは、各障がい別のプログラムを持っていたり、個人向けプログラムを一部、実施してくれる施設もあるようです。
そういう意味で民間の学童施設は、障がいをもつ子どもにとって「ちょっと『放課後等デイサービス』寄りの学童」と言える面があるかもしれません。
注:
※2) 子ども家庭庁「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」(PDF) 平成30(2018)年9月公開
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/32675809-3f98-486b-9c03-efc695ede0bb/3208a2fa/20231013-policies-shougaijishien-shisaku-000360879.pdf
※3) 「中核市」とは、東京23区「特別区」や「政令指定都市」などと比べれば、人口などの規模や自治体の権限が少し小さい市のこと(人口約20万人以上などの目安がある)。自治体が申請して「中核市」と認定されると、ここに挙げた通所支援のほか、保健所などが自治体の管理となって、地域住民の要望へ早く寄り添える公共サービスが提供できるとされる。
「発達が気になる子」に合わせた個別支援とは
では、障がいをもつ子に対する個別支援とは、何を指すのでしょうか。
端的に言えば「一人ひとりの個性や状況に合う発達・成長を目指すため、個別に計画された支援プログラム」です。実際には「個別支援計画」という計画書をきちんと作って、発達と成長に結びつく目標を定め、その達成を目指していきます。
2025年4月の国のルール改訂で、この計画書には以下の5つの項目すべてについて、長期的(1年間)、短期的(半年間)な目標・支援内容を盛り込むこととなりました。
①健康・生活
②運動・感覚
③認知・行動
④言語・コミュニケーション
⑤人間関係・社会性
そして少なくとも「本人支援」「家族支援」「移行支援(同年代との仲間づくりなど)」といった支援の方向性を明確に分け、そのうえで、①~⑤についての計画を明記することとなりました。
例として、①の健康・生活であれば、「本人」に対しては「健康状態の維持・改善」や「生活習慣や生活リズムの形成」などを目指します。
具体形には、本人の「健康状態の維持・改善」なら「健康状態の把握と対応」「リハビリテーションの実施」などとなります。本人と保護者が希望して目指す状態・状況へ向かうための、半年・1年単位の計画が細かく立てられます。
しかも、この計画には必ず「支援を受ける子ども本人」と「その親(保護者)」、両方の意思・意向が反映されます。本人や家族が希望する方向へ進める支援ができるよう、きちんと聞き取りをして、計画・実施内容が決められます。
「放課後等デイサービス」ってなに? 制度の概要をわかりやすく解説
こうした個別の計画を立てて実施していく「放課後等デイサービス」の施設は、自治体、社会福祉法人、NPO法人、営利法人(株式会社、合同会社など)によって設置・運営されます。
「放課後等デイサービス」と、未就学児対象の「児童発達支援サービス」、四肢など障害が重い子どもに対する「医療型児童発達支援」などは、
授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う※4
とルールが定められています。放課後の時間と長期休み(夏休みなど)に、障がいをもつ児童・生徒が安心して安全に過ごし、先に述べた計画に沿って、個別の支援プログラムが行われるのです(とはいえ、プログラムをこなすような強制まではされません)。
5つの領域については、お子さん一人ひとりについて計画内容を決めるため、たとえばお母さんが我が子の状況で気になる部分や、伸ばしてあげたいと思える面について、計画に盛り込むことができます。お子さん本人の「これがやりたい」という気持ちも伝えられれば、しっかり反映されます。
では実際、どんな点を本人や保護者と検討して、「本人支援」「家族支援」「移行支援(同年代との仲間づくりなど)」、さらに必要に応じた「地域支援・地域連携」(例医療機関との連携等)といった個別計画が作られ、行われるのでしょうか。
例として、国が紹介している項目を挙げておきます※5。これらについて、さらに子ども向け、親向けなど、具体的に何をどうするかを決めていくのです。
放課後等デイサービスで実施される、5領域の「本人支援」の項目例
【健康・生活】
〇健康状態の維持・改善
〇生活習慣や生活リズムの形成
〇基本的生活スキルの獲得
〇生活におけるマネジメントスキルの育成
【運動・感覚】
〇姿勢と運動・動作の基本的技能の向上
〇姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用
〇身体の移動能力の向上
〇保有する感覚の活用
〇感覚の特性への対応 等
【認知・行動】
〇認知の特性についての理解と対応
〇対象や外部環境の適切な認知と適切な行動の習得
〇行動障害への予防及び対応 等
【言語・コミュニケーション】
〇コミュニケーションの基礎的能力の向上
〇言語の受容と表出
〇コミュニケーション手段の選択と活用
〇状況に応じたコミュニケーション 等
【人間関係・社会性】
〇情緒の安定
〇他者との関わり(人間関係)の形成
〇遊びを通じた社会性の発達
〇自己の理解と行動の調整
〇仲間づくりと集団への参加
注:
※4) 厚生労働省「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」PDF 平成28(2016)年3月https//www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171u.pdf
※5) こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン(概要)」PDF 令和6(2024)年7月
https//www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/b4c800f4/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_01.pdf
放課後等デイサービスを選ぶときに確認したいポイント
そして放課後等デイサービスは、障がいをもつ子どもに対して、具体的には次のような役割を担う施設です※6。
就学している障害のあるこどもに対し、個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせて以下の支援を行う。
①本人への発達支援(本人支援)
②子どもの発達の基盤となる、家族への支援(家族支援)
③すべての子どもがともに成長できるよう、学校や特別支援学校、専修学校等と連携を図りながら、主に次の2つを支援(移行支援)
・小学生の、学童(放課後児童クラブ)等との併行利用や移行に向けた支援
・就学している期間全体のなかで、地域の一員としての役割を発揮したり、
地域の社会活動へ参加・交流できるよう支援
④こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、子どもや家族を包括的に支援
(地域支援・地域連携)
注:
※6) こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン」平成6(2024)年7月 より改変引用https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/93d83e4a-f48a-4922-befd-517fe9d7c6d4/4cc6381b/20250307-councils-support-personnel-93d83e4a-11.pdf
こうした役割を果たすべく、各事業所でさまざまなサービスが個別に提供されていきます。
ですのでお子さんの特性や希望、ご家族の「ウチの子の、ここを育てていきたいな」といった要望を、まず整理・把握してから、家族と相談して施設を選んでいくこととなるでしょう。
子どもの特性に合った支援内容か?
情報を調べてみると※7、西宮市では利用者が少人数(10人以下)設定の事業所が多い可能性が高く、また、とくに大きな駅の近辺在住者なら、自宅の近隣で複数の事業所から選べる可能性が高い状況と思われます。
放課後等デイサービスでは基本的に、集団で行う療法や、担当者と1対1で行うプログラムが、子どもや親の要望に合わせて計画的に実施されます。
西宮市内の事業所情報を見ていくと、支援プログラムの内容として独自の特色を打ち出している事業所も多いようです。具体的にピックアップしてみると2025年では
学習支援/運動療法/ソーシャルスキルトレーニング(SST)/
少人数でのゲーム・遊び/学びを含んだ集団療育/
調理のイベント/田畑作業/柔道/パソコン練習(基礎)/
英語のレッスン/プロの音楽家による音楽系の療法/アート
などがありました。
このような多くの特色の中から選べるのは都市部ゆえかもしれませんが、種類や件数に関わらず、何らかのプログラムが一つでもお子さんの特性や要望と合えば、施設へ通う楽しさが増えるかもしれません。
さらに、施設の窓口担当者とお子さんの相性の様子、近隣の様子、地域の様子なども、選ぶときにしっかり確認・検討したい項目です。
先ほど述べたようなプログラムを実施するにあたっては、さまざまな専門家が施設へ所属、あるいは連携をしているようです。お子さんに向いた、あるいは必要な専門家がいるかどうかも、選択肢の一つと言えるでしょう。
参考までに、西宮市内の施設情報に載っていた専門家の例も挙げておきます。
児童指導員/特別支援学校教諭/理学療法士/作業療法士/臨床心理士・臨床発達心理士/言語聴覚士/音楽療法士/障がい者スポーツ指導員/社会福祉士/精神保健福祉士 など
注:
※7)LITALICO発達ナビ 兵庫県西宮市の放課後等デイサービス一覧(2025年4月22日「西宮市 放課後等デイサービス」での検索結果)より抜粋引用(表現を一部変更)
https//h-navi.jp/support_facility/hyogo/cities/936/hoday
送迎や利用時間、費用面でのサポートは?
スタッフによる送迎を行うかどうかは、各事業所が決定しています。西宮市内でも、送迎があるところ・ないところがありました。送迎なしの場合は送り迎えの手配が必要となります。
また、施設の利用料は、利用者が1割負担、残りは自治体負担です。家庭への負担を軽減できるよう、各自治体で年収に応じた支払い上限額は定められています。
ただし、利用料以外の、おやつ代や制作物の材料費といった費用は、全額を自己負担で支払うこととなります。
自治体によってはさらに、独自の補助サービスを取り入れているところもあります。情報を調べたり事業所に確認するなどして、必要なら利用前に申請等の手続きを行いましょう。
見学・相談のしやすさとスタッフ体制もチェック
施設では、すでに在籍している利用者のケアも大切ですので、見学は必ずしも好きなタイミングで、すべてを自由に……とはならないかもしれません。
ネットや電話等で事前に日時予約をし、まずはご家族が、できればご本人も一緒に(あるいは2回目以降に)行って、施設の雰囲気や立地条件、スタッフや利用者の様子などをぜひ、肌で感じてみてください。時間や曜日を変えて2回目の見学をするのも可能なはずです。
また、その施設に対する質問や児童発達支援に関する疑問にも、スタッフに質問すれば答えてくれると思います。
子どもも家族も安心して通えることがいちばんですので、可能であればいくつか見学に行き、施設ごとの特色を知ることもおすすめします。
ケア21の「リールス」が選ばれている理由
ここからは、放課後等デイサービスの詳細例として、ケア21が運営する「リールスメイト」の支援をご紹介します。
放課後等デイサービスがどういうものかという実例を具体的にお伝えするため、また、個人情報保護等のルールを守る観点からも、ケア21の情報を例に挙げます。ご了承ください。
療育・遊び・生活支援がバランスよく受けられる
国のガイドラインでは、とくに本人への支援で「自立支援と日常生活の充実のための活動」「体験的な活動や遊び」「地域交流の機会の提供」「こどもが主体的に参画できる機会の提供」を組み合わせながら計画を立てることとされます。
これを土台とするリールスメイトの個別支援プログラム(療育プログラム)には、たとえば次のような種類があります。
・創作活動
・身体活動
・SST(ソーシャル・スキル・トレーニング)
・ICT活動
・レクリエーション ・外出活動 など
このうちの創作活動であれば、
〇季節感を知る・味わうための季節の創作
〇皆で楽しむ、集団としての一体感を得るためのビッグアート
〇想像力や表現力を養うためのアイロンビーズ
などが、個人の希望や計画に沿って実施されます。また、学校の宿題・課題への支援も行われます。
一人ひとりに寄り添った支援プログラム
リールスメイトでは、お子さんの将来を見据えて「社会性を高める支援」と「基礎運動力を高める支援」に力を注いでいます。以下に、その説明文を紹介します。ある施設が、なぜそのようなプログラムを選んでいるのかという「施設としての意図」が伝わる事例かと思います。
社会性を高める支援
①相手に自分の気持ちを上手に伝えること
②仲間をはじめ周囲の人たちを思いやること
③ルールを守ってみんなで行動すること
リールスメイトでは、この3つの能力を高める支援を重視しています。みんなと一緒にゲームなど遊ぶことを通して、自分の思いを伝える楽しみを感じます。
みんなと協同で物を作ることを通して、相手の気持ちに気づく喜びを感じます。
おやつや食事など、みんなと決められた同じ時間を過ごすことで、ルールを守らなければいけない理由を知ります。
このように様々な活動を通して、お子様が必要な社会性を身に着ける支援をしてまいります。
基礎運動力を高める支援
リールスメイトでは、運動機能を高めることが心身の発達に影響することに注目しています。
散歩をしたり、近隣の公園への外出時に体操をしたり、音楽に合わせてダンスをするなど、全身を動かすことを積極的に取り組んでいます。
適度の運動は、目から入る情報を認知する機能と脳から手足への運動指示とのバランスを整えるのに有効であるとされ、とくに成長期にあるお子様には必要です。
また、体を思う存分動かすことは集中力を高めることにつながります。運動が得意ではないお子様でも、できる範囲で運動を促すことで体を動かす楽しみを覚えていただきます。
このように運動を通して、お子様の心身の成長を支援してまいります。
具体的なプログラム内容として、リールスメイト摂津別府(せっつべふ)のものを例として掲載しておきます。
これは開設1年後から公表を義務付けられている書類ですので、さまざまな施設で、ホームページ等に掲げられていると思います。

ケア21では「リールスメイト」と、放課後等デイサービス・児童発達支援で重症心身障がい児対象(未就学児~高校3年生対象)の「リールスメディカル」で、こうしたプログラムの情報を掲載しています(施設名の下にあるPDFにてご覧いただけます)。
ケア21ホームぺージの事業所一覧(各施設の名称の下に「自己評価表/支援プログラム」というPDFリンクがあります)
〇リールスメイト
〇リールスメディカル
そして1日の過ごし方は、リールスメイトでは、たとえばこのようになっています。
〇平日の一例
14:00ごろ 送迎車到着(各学校終了時で異なる)/更衣・トイレ(確認)など・
それぞれの活動準備
↓
14:30ごろ 個別支援プログラム・訓練①(個別支援プログラムの中から組み合わせて実施)
↓
15:30ごろ おやつ・休憩
↓
16:00ごろ 個別支援プログラム・訓練②(個別支援プログラムの中から
組み合わせて実施)・帰宅準備・送迎車順次出発(第1便)
↓
17:30ごろ 個別支援プログラム・訓練③(個別支援プログラムの中から組み合わせて実施)
↓
19:30ごろ 帰宅準備・トイレ(確認)・送迎車出発(第2便)
西宮市内で、複数拠点展開予定。送迎ありで通いやすさも◎
リールスでは、阪急神戸本線・今津線 西宮北口駅徒歩7分のところに、放課後等デイサービス「リールスメイト」を2025年8月にオープンします。
また、1対1の個別支援を提供する「リールスプラス」も、2025年秋に同地で開設予定です(メイトとは部屋が分かれます)。
リールスプラスは、リールスメイトとの併用も可能です。 また、リールスメイトでは送迎が可能で、必要な方の相談に応じます。
「リールスメイト」を実際に利用している保護者の声
リールスメイトを実際に利用いただいている保護者の方の声は、リールスのホームページに掲載されています。質問事項は「サービスをご利用になっていかがでしたか?」というものでした。2つほどご紹介します。
「いつも楽しく通っています」
母親である自分が働くことになり子ども通う事業所を探していたところ、ちょうど家の近くにある事業所で定員に空きが出たのを知り、それがきっかけで利用を始めることになりました。
本人はいつも楽しく通っています。本人の将来の就職も視野に入れて毎回のように違う課題をいろいろと考えてもらい、取り組んでいます。
事業所で定期的に行われるイベントも毎回楽しみにしています。 いつもありがとうございます。
「交流を広げることができました」
学童保育に小学校3年生まで通っていました。同じ学校の同じ支援学級で、同級生のお友達が事業所に通っていたことがきっかけで、利用を始めることになりました。
事業所を利用する中で、通っている他の学校のお友達と仲良くなり本人の交流を広げることができました。
年上・年下のお友達にかわいがってもらっているようです。 本人が笑顔でいられることを親として安心に感じています。
その他のリールスメイトご利用者の声はこちら
https://rirus.jp/rirus_cat/mate/
リールスのご利用方法・お問い合わせの流れ
リールスメイト、リールスメディカルの施設は、2025年4月現在、以下のように展開しています(郵便番号順に掲載)。
〇放課後等デイサービス・児童発達支援(小学1年生~高校3年生対象。一部施設で未就学児「児童発達支援」も別室にて対応あり)
リールスメイト
| リールスメイト足立花畑 | 〒121-0061 東京都足立区花畑五丁目12-1 花畑団地第82号棟102号室 |
| リールスメイト新小岩 | 〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩五丁目17-11 ウインズビル101 |
| リールスメイト東向島 | 〒131-0032 東京都墨田区東向島五丁目7-12 若草ビル1階 |
| リールスメイト加島 | 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島三丁目中 2-16 KSビル1階 |
| リールスメイト豊里 | 〒533-0013 大阪府大阪市東淀川区豊里五丁目21-3 アローウィング栄光101号室 |
| リールスメイト蛍池 | 〒560-0045 大阪府豊中市刀根山三丁目1-22 第5プロビナンス村橋1階 |
| リールスメイト千里丘 | 〒566-0001 大阪府摂津市千里丘五丁目3-17 101号室 |
| リールスメイト摂津別府 | 〒566-0042 大阪府摂津市東別府二丁目8-1 1階 |
| リールスメイト茨木郡 | 〒567-0072 大阪府茨木市郡五丁目22-34 1階 |
◎2025年8月1日オープン◎
リールスメイト西宮北口
| リールスメイト西宮北口 | 〒662-0841 兵庫県西宮市両度町6-22 ベルシャイン西宮201 |
※個別療育支援サービスの「リールスプラス西宮北口」は2025年秋オープン予定
〇重症心身障がい児対象 放課後等デイサービス・児童発達支援(未就学児~高校3年生対象)
リールスメディカル
| リールスメディカル足立花畑 | 〒121-0061 東京都足立区花畑三丁目33-6 エクレールメゾンスズキ101号室 |
| リールスメディカル井高野 | 〒533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野二丁目7-28 |
| リールスメディカル吹田山田 | 〒565-0824 大阪府吹田市山田西一丁目1-2 エクセル千里101号室 |
| リールスメディカル茨木玉島台 | 〒567-0850 大阪府茨木市真砂玉島台5-9 1階 |
| リールスメディカル高槻 | 〒569-0825 大阪府高槻市栄町一丁目20-26 ヴェルデ高御座1 |
リールス各施設のご利用に際しては、次のように手続きを進めていただきます。
ご利用までのステップ
お問い合わせ
→施設見学・面談
→自治体での受給者証の発行手続きと発行(ご家族様自身での申請が必要です。ご不明な点はお手伝いいたします)
→ご契約のお手続き
→ご利用開始
まずは受付で見学日程を決めていただき、各施設への見学の場で具体的なご希望などをお聞かせください。
〇お問い合わせ先
ケア21受付センター フリーダイヤル:0120-944-821
(9:00-18:00 年末年始などに休業あり)
以上、放課後等デイサービスの概要と実例をざっとご紹介してきました。
子育てで外部の手を借りることは、お子様にとっての支援、ご家族にとっての「レスパイト(休息)ケア」になると考えています。
本記事の内容が、少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。 ご覧いただき、ありがとうございました。
介護施設ブランド
多様なシニアライフにお応えする有料老人ホーム「PLAISANT(プレザン)」シリーズ、
認知症グループホーム「たのしい家」、小規模多機能型居宅介護「たのしい家」。
ご利用者様の用途に応じて施設シリーズを展開しています。
TOP